今回は、社長キャラバン後の懇親会に参加して思った事について触れさせていただきます。
今回の社長キャラバンの内容と目的(6月12日開催)
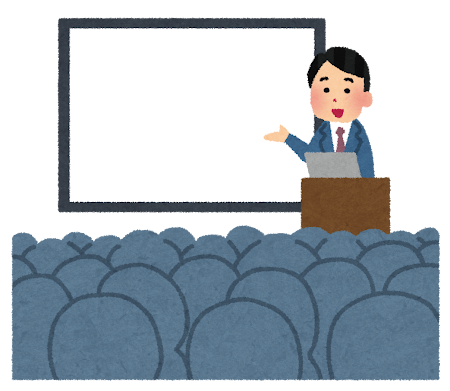
まず初めに、今回の社長キャラバンの内容について触れさせていただきます。元々の社長キャラバンは、4月25日に全社員に対し、東京事務所でのリアル参加組(各エリア勤務社員にもリアル参加依頼あり)とオンライン会議参加組(Teams会議)の同時参加で実施され、説明内容は今年度の当初事業計画でした。
それに対し、今回の社長キャラバンは、関西エリアの事業所に勤務する社員に対し、物件視察も兼ね、リアル説明と対話会を目的に実施されたイベントだと理解しています。
したがって、社長が説明される内容は、前回とほぼ同じで、個別に地域性が反映された内容が追加されたものだったと理解しています。その後の対話会については、直接関西エリアの社員の生の声を聞きたいというのが主催者側の目的だったと理解しています。
そのような私なりの受け止め方を踏まえ、コロナ前の完全出社時代の感覚と、その後のリモートワークを5年間経験した後の感覚の違いについて触れさせていただきます。
コロナ前の完全出社時代の感覚
私の感覚になりますが、この頃は、大半の人が似たり寄ったりの感覚だったと想像します。その前提で、この頃は、当然のように、各エリア単位の社長キャラバンは開催されるものだと思っていました。そして、その説明会へはリアル参加が当たり前だと思っていました。
その感覚を私風に言い換えると、毎日出社して仕事している。その延長線上のイベントって感覚です。
コロナ禍からのリモートワークを5年間経験した感覚
これも私の感覚になりますが、同じ内容をエリア別に社員のリアル参加で実施する必要ってあるの?って感覚を強く感じています。
主催者側は、リアル参加で実施しないと社員が本当に説明を聞いてるかどうかわからない不安や、聞いてる社員の空気や熱量がわからない不安があるのかもと想像はできるのですが、リモートワークを5年間続けてきた私からすると、いまだに、何をズレた感覚を持ち続け社員と接しているのかと思ってしまいますし、同じ事をするなら、全体説明をやった後、エリア別にリモート会議で個別実施すれば良いだけというのが素直な感覚になっています。
その理由は、完全出社時代のリアル参加でも、聞く人は聞いていたし、聞き流す人は上手く聞いているふりをして、聞き流していたからです。これをリモート会議で行なっても、同じだと思えるからです。
懇親会の状況

社長キャラバン後に場所を変えて実施された懇親会の状況は、まず参加者数について、全社員の内1/3程度の参加になっていたようです。これは、完全出社時代の懇親会がほぼ全員参加になっていた事を思うと、驚きの少なさになってきたんだなと驚きました。この参加人員数についての私の感想は、そりゃ、そうなるでしょう。っていうのが、正直な感想でした。
また、主催者側は、この現実を受けとめ、旧態依然とした発想から、リモートワークをへて生じた考え方の変化を理解し、社員へのアプローチの仕方を変えるべきだと思いました。
次に、懇親会に恒例の催し物の開催です。これは、参加人数が少なくなっても、以前同様の発想で行われていました。メインの参加者は、若手社員です。このやり方も、私的には、如何なものかな?って思いがあります。いつまで昭和の感覚を引きずっているの?って思いです。確かに、場を盛り上げる事には寄与しているのですが、若手はどう思って参加し演じているのか。
また、その努力が、働き方が多様化している中で、どう報われるのか。などなど、私の頭の中では、ハテナマークが、何個も出てきました。
まとめ
久々に、懇親会に参加し、感じたことは、これって、いま時、必要な営みなの?って言うのが、正直な感想です。
せっかく、コロナ禍で大半の人がリモートワークを経験したのに、社員の気持ちを掴む手段として、この手の行事も、今風に工夫しないと、主催者側の思いと受ける側の思いのギャップが大きくなるばかりなのでは?って思いました。コロナ禍の働き方を経験した今、人と人との繋がり方について、コロナ前の方法が果たして最適なのか?って事を、じっくり成果と業績を結びつけて考える必要があるのではと改めて感じた出来事になりました。


