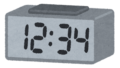今回は、アフターコロナ後初の京都嵯峨野散策について記載させて頂きます。
季節は、2023年11月下旬で場所は嵯峨野界隈になります。
新型コロナウイルス感染症前の状態
当時の嵯峨野は、インバウンドブームという事もあり、日本人+海外の観光客が押し寄せ、人また人って感じで、メジャーな観光名所は、溢れかえっていました。また目的場所へ辿り着くまでの道中もしかり、食事処も長蛇の列になっていました。
もう、観光どころで無い状態って感じでした。観光地にお住まいの住民の方々も大変な思いをされていたと想像します。
新型コロナウイルス感染症対策期間中の状態
この期間中の嵯峨野は、ほぼ日本人のみの観光客で、それも少数になっていました。道も店も閑散としており、閉まっている店もあったくらいで、コロナ後の回復は大丈夫だろうかと心配になったくらいです。
ただ、観光している側からすれば、人混みを気にする事なく、存分に観光ができて得した気分になれたタイミングでもありました。
新型コロナウイルス感染症5類移行後の状態
5類移行後の嵯峨野は、コロナ禍が嘘のような状態になっており、道も観光地も店も多くの観光客で溢れかえっていました。それも、海外からの観光客の多さに驚きました。
これは、円安の影響で、日本への旅行がかなりお得になっている事も大いに関係していると思います。
そんな中、私が今回訪れた観光名所を下記に紹介させて頂きます。
野宮神社(ののみやじんじゃ)
こちらの神社は、阪急嵐山駅又は嵐電嵯峨駅で降りてから、竹林を抜けた先にある神社で、その昔、天皇の代理で伊勢人軍にお使えする斎王が、伊勢へ行かれる前に身を清められた所だそうです。
こちらは日本最古級様式の鳥居や神石(亀石)や苔の絨毯があるところです。何より有難いのは、無料拝観できる神社となっています。
常寂光寺(じょうじゃっこうじ)
こちらは、関ヶ原合戦の西軍敗北に繋がった裏切りで有名な小早川秀秋や豊臣家が関係しているお寺のようです。また、裏山は新古今和歌集や百人一首で有名な藤原定家がこもっていた小倉山荘跡もあります。
このお寺の紅葉シーズンは、多くの観光客で溢れかえる名所となっております。拝観料は、ちょこっと高めな感じもしますが、石段を登り本堂へ向かう拝観コースは紅葉のトンネルのようになっており、人気があるのも納得できる名所だと思います。


祇王寺(ぎおうじ)
こちらは、平家物語にも登場する平清盛の寵愛を受けた白拍子の祇王が、晩年母と妹とともに出家、入寺した悲恋の尼寺だそうです。
紅葉シーズンは、紅葉の赤と苔の青さが際立つ、見応えのある名所となっています。場所は嵯峨野の外れにあるので、観光客もそれほど多くなく、ゆっくり建物内で座って庭を眺めることができるお勧めスポットだと思います。



宝筐院(ほうきょういん)
こちらは、足利二代将軍「足利義詮」の菩提寺になっています。このお寺には、南朝側に付いていた楠木正成の息子の「楠木正行」のお墓もあります。
こちらのお寺は、女性専用の宿坊にもなっており、紅葉と庭の苔の緑が映えるお勧めスポットです。紅葉真っ盛りの時は、観光客が庭に入った途端、「わぁ〜〜ぁ!」って声をあげ立ち止まって、庭の綺麗さに見惚れてしまう光景に、しばしば遭遇します。本堂にも上がることが可能で、畳の部屋に座り、庭を眺める観光客も沢山おられます。ここは、嵯峨野で私の一番のお気に入りスポットとなっています。



鹿王院(ろくおういん)(番外編)
今回は訪問できなかったのですが、こちらは足利三代将軍「足利義満」が、金閣寺を建てる前に建立したお寺だそうです。パンフレットには、若き日の一休さんも修行されていたとの記載もあります。このお寺も女性専用の宿坊になっているそうです。このお寺のお勧めは、紅葉シーズンの山門からの道中の紅葉がとっても綺麗なところです。また、本堂の縁側に座って眺める苔の生えた庭を眺めているのも、良いひと時の過ごし方だと思います。




感想(まとめ)
新型コロナウイルス感染症の5類移行後に訪れた嵯峨野は、すっかりコロナ前の状態に戻っていたように感じました。海外観光客の国別構成比は以前と変わっているように感じましたが、円安のお得感もあり、海外からの観光客で賑わっていました。私が思う嵯峨野は、秋の紅葉シーズンが一番お勧めだと思っています。見所が沢山あるので、お勧めの観光名所です。
何にしても、在宅勤務を続けている中、休日の外出は貴重なリフレッシュの機会となっております。