今回は、新型コロナウイルス対策としてリモートワークを始め5年が経過したタイミングで、私なりに色々思う事を記載させていただきます。
結論から先に述べさせていただきますと、リモートワークは実施可能業務であっても、仕組み作りや人の性質に影響するデリケートな働き方だという事です。それらの理由について、これから記載させていただきます。
リモートワークに必要となる条件
下記に、私が思うリモートワークをする為に必要となる条件(物的・人的)を記載させていただきます。
ハード面
インターネット環境面(必須)
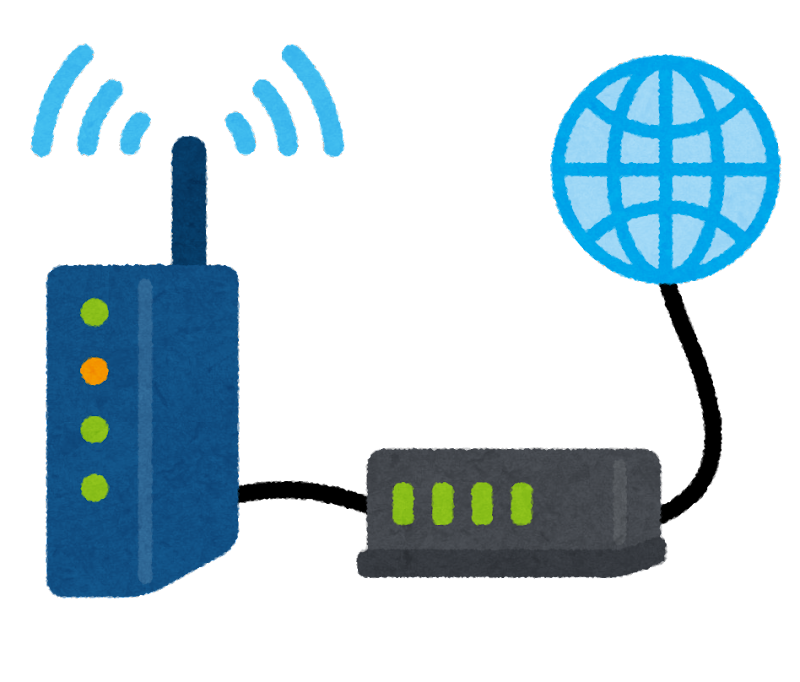
こちらは、リモートワークを行う上で必須環境となります。インターネット環境がない状態でのリモートワークは、そもそも実施不可となります。理由は、社内LAN環境への接続も不可能になり、結果、必要なデータへのアクセスや業務システムへのアクセスも不可能になります。
よって、インターネット環境が整ってない方が、リモートワークを行う事は不可能です。
また、ポケットWi-Fiやスマホのテザリング機能で、リモートワーク作業を行おうとする方もおられますが、これらの環境は急場凌ぎは出来たとしても、継続的なリモートワークは、ほぼ不可能です。理由は、回線の安定性とスピードに問題があるからです。こちらの利用シーンは、急に自宅のインターネット回線が利用出来なくなった場合や、外出先での接続や、災害等の為、急遽出社勤務が不可能になった場合の緊急措置的な対応時のみ許可すべきです。
作業環境面

こちらは、リモートワークの作業場所の環境が整えられているかって事になります。わかりやすく例えると、会社の事務所と比較し、遜色ない程度に整備されているかです。作業場所や机や椅子が整えられており、長時間の作業に耐えうる状態になっているかどうかという事になります。この環境が整っていないと、仕事どころの話にならないからです。こちらは、非常に大事な項目になります。
会社がこれらの整備費用の一部でも負担してくれると良いのですが、そうでない場合は、自費で整備する必要があります。また、作業用のノートパソコンを貸与されている場合は、外付けディスプレィや外付けキーボードが必要になります。理由はノートパソコンの作業では、画面が狭く作業効率が下がる人が多いからです。
この職場環境の整備が不可能な場合は、継続的なリモートワークは無理で、作業環境が整っている会社の事務所で作業していただく必要があります。
ソフト面(内面・知識)
次は、ソフト面について触れていきます。
ITスキル面
こちらの能力も、リモートワークをする上で、必要不可欠のスキルになります。例を挙げると、自宅にインターネット環境が整備されていても、パソコンをWi-Fi接続できないと、インターネット環境がない状態と同様だからです。要は、何も仕事が出来ない状態です。
また、パソコンの操作方法がわからない人も同様です。たとえ、家族の誰かにインターネット接続してもらったとしても、その後は、一人で作業をする事になります。その場合、パソコンの操作方法がわからない人は、何も出来ません。出社していた頃は、隣に誰かがいて、わからない事は、他の人にやってもらって凌いでいたとしても、リモートワークになった途端、隣に誰もいないため、自分で対処する必要があります。それが出来なければ、結果、ただ家にいるだけで、なんの役にもたてません。
この現実は、物凄い事で、その人達もコロナ前は、会社で共にパソコンを使って仕事をしていた人達です。その人がリモートワークになった途端、何も出来なくなったのです。それは、戦力になっていると思っていた人が、実は全く戦力になっていなかった現実をあぶり出した事になります。要は、今まで見えにくくなっていた事実が、リモートワークを行なった事により表面化された事になります。
私の実感では、厳し目に判定するなら5割の人が、甘目に判定するなら3割の人が、このタイプの人に該当します。
そりゃ、5類移行後、一気に出社回帰が進むはずだと思った次第です。その人たちの仕事してる感をアピールする場所は、職場しか選択肢が無いからです。でも、やれる事は、限られますが。
リモートワーク向けの作業方法の構築
こちらも非常に大事な営みになります。コロナ前の作業方法でリモートワークを進めようとしても、100%無理です。理由は簡単で、コロナ前は、紙資料ベースの作業になっています。この作業を改めなければ無理です。よって、まず一つ目は、資料のファイル化です。
次に必要となるのが、作業の可視化です。今、誰が、何をして、どこまで進捗し、どれだけ完了しているのか。この状態が可視化できる仕組みになっていないと、作業に偏りができたり、タイムリーな作業指示ができなくなったり、生産性の悪化や品質の悪化に直結します。要は、仕事の方法を変え、あたかも誰もが同じ場所で仕事をしてるかのような状態を作り出す必要があるという事です。この二つの仕組みが構築されていなければ、継続的なリモートワークは、上手く機能しません。この仕組みが構築されいれば、前項で記載したITスキルに問題がある人でも、なんとか戦力化が可能になります。それほど、重要な仕組みになるという事です。
私が想像するに、この仕組みが構築出来ないマネージャーが多いから、仕方なく優秀な方も含め全員出社回帰せざるを得ないのだと想像しています。裏を返せば、この仕組みが構築出来ていれば、生産性や品質を落とす事なく、リモートワークが可能になるという事です。
思考面
こちらは、リモートワークをする本人の思考面になります。こちらにも特性があり、まずは、一人でも孤独感を感じる事なく、自己コントロールでき、作業に集中できるタイプか否かになります。一人では寂しく不安になるタイプの人は、継続的なリモートワークには、向いていないと思います。それは、作業に集中できないからです。
次は、思考方法が能動的か受動的かの切り口になります。リモートワーク向きの思考方法は、能動的タイプになります。何事も自らチャレンジするタイプです。このタイプの人は、アクシデントを一人で乗り切る事も可能になります。
それとは逆に受動的タイプの思考方法の人は、全て受け身なので、何か指示があるまで待つタイプです。これでは、基本一人で作業を行うリモートワークには不向きになります。この不向きな人をリモートワーク可能にさせる有効な仕組みが、先ほどの作業の可視化になります。このタイプの人は、作業の可視化が構築されていない限り、リモートワーク不可タイプと認識していた方が良いと思います。
もう一つ大事な切り口が、自責思考タイプか他責思考タイプかになります。リモートワークに向いているタイプは、自責思考タイプです。このタイプは、同じ過ちを繰り返さないタイプです。それに対し、他責思考タイプは、同じ過ちを繰り返しがちになります。リモートワークの場合、ミスの自己申告は非常に大事な行為となり、そのミスの原因を断つ行為も非常に大事になります。これができるタイプが自責思考タイプの人だと思っています。
思考の柔軟性
思考方法が柔軟な人の方が、リモートワークには向いていると感じています。理由は、新しい働き方だけに、今まで経験してなかったような事象に遭遇し、それを受け止め解決していく場面が多くなるからです。その場合、柔軟な思考ができる人の方が、自力で乗り切れるケースが多いです。
逆に、頭が硬い人は、過去の前例や過去の仕事の仕方に縛られ、新しい発想が芽生えにくい為、自分で解決できず、フリーズする人が多くなりがちです。その場合、他の人の手助けが必要になり、その分生産性が落ちる事になります。また、このタイプの人は、完全出社時代の仕事のやり方から抜け出せず、結果、出社回帰に向かうという流れになるのだと想像しています。
業務スキル面
こちらは、リモートワークに関係なく、誰しも有していて不思議でないスキルなのですが、コロナ前は、同じ仕事をしている人が周りに沢山いたため、作業に行き詰まった時、隣の人に聞けば解決していました。その為、当事者の認識もそんなに問題意識を持っていない人が多かったと想像しています。その証拠に、リモートワークになり一人で作業するようになった途端、フリーズする人がいました。理由は、満足な業務スキルを有していなかったからです。逆にいえば、コロナ禍のリモートワークで、その現実を受け止めスキルを付けた人も多かったと思います。リモートワークは、良いリトマス試験紙になり、良い育成の仕組みだともいえます。
一番マズイケースは、業務スキル面で問題があり、かつITスキル面も問題がある人です。このタイプは、リモートワーク以前の問題になり、出社回帰しても問題山積になるだけの要注意人物になります。
私が思う出社回帰が進んだ理由
新型コロナウイルス感染症5類移行後、リモートワークに向いている業務にも関わらず、出社回帰が一気に進んだ大きな原因の一つは、上記に記載した項目をクリア出来なかった会社や職場が多かった為だと想像しています。私が5年間経験した結果、リモートワークは、環境や人を選ぶ働き方であり、対応を誤ると生産性も落ち、コミュニケーション不足と相まって、悪い方向に向かうケースが多くなる、意外と難易度の高い働き方だと思います。
その為、その努力をするより、前の働き方に戻した方が、手っ取り早い為、出社回帰したがるのだと想像しています。私の会社でも、他の部は月数度のリモートワークを混ぜながら、大半が出社回帰しています。ただ、出社回帰している人の中にも、本当なら継続的なリモートワークをしたいと思っている人や、リモートワークが向いてるタイプの人も多くおられると想像しています。出社回帰は、そういう人の芽を詰む行為にもなり兼ねないので、仕事を預かっている管理者は、工夫をする義務があると思います。
また、そうする事により、一極集中(都市部集中含む)や過疎化問題や少子高齢化問題の解決にもつながると信じています。それが、今、逆行している現実が、非常に寂しく感じられてます。
まとめ

以上のとおり、リモートワークは、意外と難易度の高い働き方とは思いますが、工夫次第で、非常に可能性が広がる働き方だと実感しています。私的には、この新しい働き方を自ら放棄する事は、大きなものを失う行為だと思っています。今後是非、リモートワーク可能業務については、導入率が上がり、地方や田舎でも人口が増えていく日本が蘇ってくれることを期待して止みません。リモートワークは、その一助となる働き方だと信じております。


